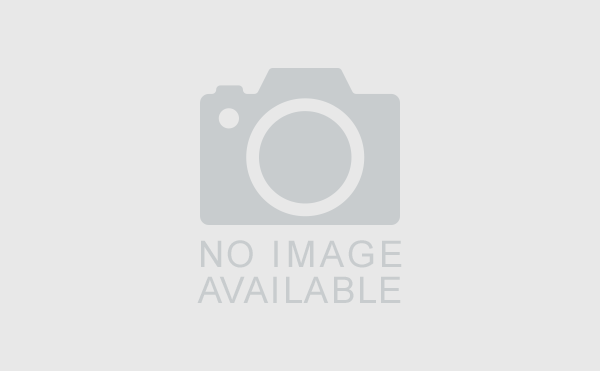ご飯のお話・HILL’Sさんのセミナー

腸と腎臓のつながり「腸腎相関」について
今回は、フードメーカー「HILL’S」さんのセミナーで学んだ内容をご紹介します。 セミナーのテーマのひとつに「腸腎相関(ちょうじんそうかん)」という考え方がありました。これは、腸の環境が腎臓に影響を与え、腎臓の状態も腸に影響を与えるという、双方向の関係を指します。
特に腎臓病の動物では、この関係がとても重要になります。 腎臓の働きが弱くなると、腸内の善玉菌と悪玉菌のバランスが崩れ、悪玉菌が増えてしまいます。その結果、腎臓に負担をかける毒素が作られ、炎症や繊維化が進行してしまうことがあります。 これが「負の腸腎相関」と呼ばれる悪循環です。
食物繊維の役割
この悪循環を断ち切るために注目されているのが「食物繊維」です。 食物繊維は腸内細菌のエサとなり、体に良い短鎖脂肪酸などの有益な物質を作り出します。これらの物質は腸内環境を整え、悪玉菌が増えにくい状態を保ちます。さらに、免疫細胞の働きを助けたり、炎症を抑えたりする作用もあります。
腎臓病の動物にとっては、尿毒素の減少や腎臓の炎症・繊維化の抑制が期待できるため、食物繊維を取り入れることで、腸腎相関を良い循環へと導くことができます。
注意点とおすすめのフード
ただし、食物繊維をフードに加えようとすると、リンなどのミネラルも一緒に増えてしまうことがあります。特にリンは腎臓に負担をかけるため、果物や野菜を自己判断で与えるよりも、ミネラルバランスが調整された動物用フードを選ぶことが大切です。
また、食物繊維にも種類があり、それぞれ働きが異なります。 そのため、複数の食物繊維をバランスよくブレンドしたフードを取り入れることが効果的です。
今回のセミナーで紹介されていた「HILL’S 腸内バイオーム」は、こうしたポイントをしっかりカバーしているフードです。ただし、腎臓用フードと比べるとリンの含有量がどうしてもやや多いです。
その為、腎臓病の管理には定期的なリン数値のモニタリングや、リン吸着剤の併用などの工夫が必要となりそうですが、ここがうまくいけば良い腸腎相関が維持されて、腎臓病の子がより健康的に長生きできる期待があります。
当院ブログは獣医師佐藤(洋)が作成しております。
ご不明な点がございましたら、お気軽に診察時間内にお尋ねください
お気軽にお問い合わせください。047-447-5858診察時間9:00-12:00/16:00-19:00
[土日は17:00迄]
*休診:水,祝 手術・往診時間は電話対応ができない事があります。